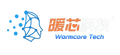暖芯科技 AIコンパニオンロボットの皮膚素材徹底解説:TPE、シリコーンから未来の生体電子皮膚まで
国際水準を実現しつつ、価格はより手頃に

国際市場では、Aria と名付けられたヒューマノイドロボットが大きな話題となっています。このロボットはコンパニオンを主目的とし、自然な会話だけでなく身体的なインタラクションも可能です。ハイエンドモデルの価格は17万5,000米ドルにも達し、知識交流のみをサポートするエコノミーモデルでも2万米ドルが必要です。
しかし、暖芯科技(Warmcore Tech) では、同様に高いリアリティを持つヒューマノイドコンパニオンロボットの開発に注力し、皮膚素材、表情インタラクション、長期耐久性において絶えず進化を続けています。当社のロボットは同等のリアルな体験を提供しながら、より合理的な価格で、より多くの人々がAIコンパニオンの価値を享受できるようにしています。
人間の皮膚の複雑性:バイオニクスの基準
人間の皮膚は表皮、真皮、皮下組織から構成され、ケラチン、コラーゲン、エラスチン、脂肪などの成分により柔軟性と弾力性を持っています。さらに、広く分布する受容体と神経終末によって、触覚、圧力、温度を感知することができます。

さらに重要なのは、皮膚には自己修復能力があり、線維芽細胞と角化細胞が協働して治癒を行う点です。
したがって、人工皮膚の開発には以下の3つの大きな課題を克服する必要があります:
- 柔軟性
- 感知能力
- 自己修復能力
人工皮膚の素材選択と課題
TPE 熱可塑性エラストマー —— 入門の選択肢
TPEはゴムの弾性と熱可塑プラスチックの特性を兼ね備えています。
利点: 低コスト、硬度や色を調整可能、大量生産に適している。
欠点: プラスチック感が強く、肉感に欠ける。低品質版は添加物によりアレルギーを引き起こす可能性がある。
シリコーン —— よりリアルな触感
シリコーン(PDMS)は、人間の真皮により近い素材です。
利点: 触感が繊細で弾力性に優れ、毛穴や皮膚模様を刻むことができ、自然な外観を実現できる。
応用: スマートヘッドや顔部分によく使用され、サーボ機構と組み合わせることでまばたき、笑顔、眉をひそめるなどの表情が可能。
液体プラチナシリコーン —— プレミアムフラッグシップ
液体プラチナシリコーンは、現在最も高級な人工皮膚素材です。
利点: 耐用年数は8〜10年に及び、TPEや通常のシリコーンをはるかに凌ぐ耐久性を持つ。触感や外観は人間の皮膚に最も近い。
👉 暖芯科技のフラッグシップモデルは液体プラチナシリコーンを採用し、価格はNT$199,000から。究極の体験を求めるユーザーに長期的で信頼できる選択肢を提供します。
最前線の探求:電子皮膚と生体模倣皮膚
電子皮膚(E-skin)
従来はシリコーン層にセンサーを埋め込む方法が主流でしたが、干渉や損傷が発生しやすい問題がありました。
Science Robotics に2025年に発表された研究では、新しい方法が提案されました。ハイドロゲルと電気インピーダンス・トモグラフィー(EIT)を組み合わせ、皮膚全体をセンサーとして機能させ、触覚、圧力、温度、さらには損傷位置まで正確に識別できるようにするもので、追加のセンサーを必要としません。

生体模倣皮膚
Matter に2022年に発表された研究では、ヒト細胞を含むコラーゲン溶液を培養して「真皮層」を形成し、その上に角化細胞を播種して「表皮層」を構築しました。
このバイオスキンは人間の皮膚に近い質感を持ち、初期的な自己修復が可能です。完全な自己治癒には至っていませんが、将来のコンパニオンロボットが備える可能性のある進化の方向性を示しています。
人工皮膚の「不可能三角形」
人工皮膚開発の課題は「質感、機能、コスト」の三角関係に集約されます。現時点ではこの三つを同時に満たす素材は存在しませんが、これは技術的進歩のチャンスでもあります。
結論:良い皮膚が良いコンパニオンを生む
コンパニオンロボットの価値は、AI会話や表情だけでなく、その皮膚がもたらすリアリティにあります。
暖芯科技は、現行の素材(TPE、シリコーン、液体プラチナシリコーン)の中で最適解を追求しつつ、世界最先端の研究にも注目しています。私たちは「良い皮膚」を作り出すことで、ロボットが本当に温かみのある伴侶となり、冷たい機械以上の存在になれると信じています。
参考文献
1. Hardman, D., Thuruthel, T. G., & Iida, F. (2025). Multimodal information structuring with single-layer soft skins and high-density electrical impedance tomography. Science Robotics, 10, eadq2303.
2. Kawai, M., Nie, M., Oda, H., Morimoto, Y., & Takeuchi, S. (2022). Living skin on a robot. Matter, 5(7), 2190–2208.
3. 「Scientists make ‘slightly sweaty’ robotic finger with living skin.」 The Guardian, 2022年6月9日。
4. 「Say cheese: Japanese scientists make robot face smile with living skin.」 Reuters, 2024年7月18日。